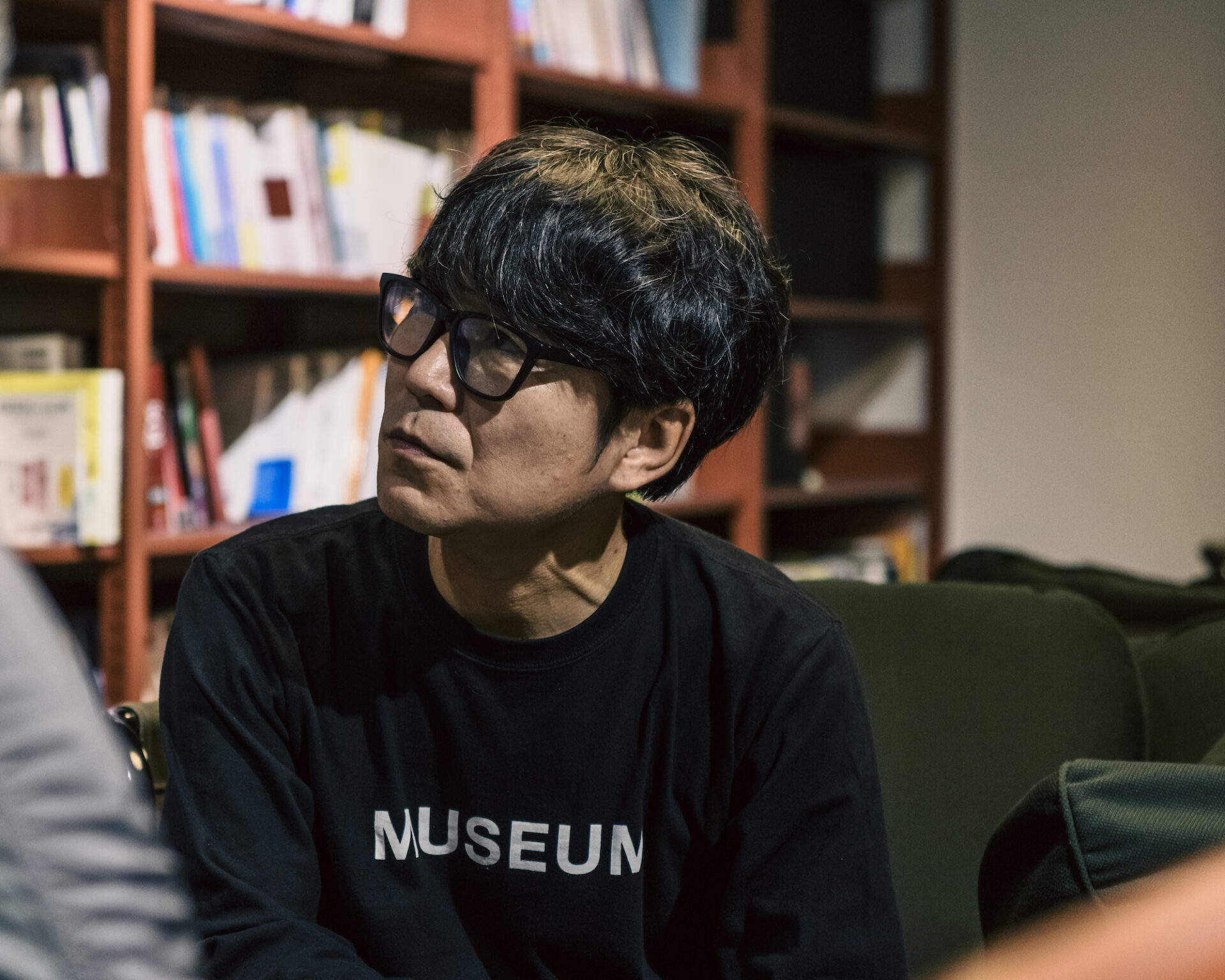2025-07-03
Vol.18
フリーター(ビジネスコンサルタント)
長瀬次英 氏(後編)
-
KPIは本質から導き出せ
-
SNSの罪深さ
-
デジタルを活用し、リアルで本質的な価値を楽しむ
-
目指すべきは、美しいガラパゴス
“経営の神様”と呼ばれた人がいた。100年以上前に現在のパナソニックホールディングスの前身である松下電気器具製作所を起業した松下幸之助だ。そんな彼が生前残した言葉に、「正しい経営理念というものは、基本的にはいつの時代にも通ずるものである」という一節がある。ここでいう“正しい”とは、人が幸せになるための経営を指す。
生活の隅々にデジタルテクノロジーが浸透し、“過度なデジタル依存は人を不幸にする”と言われる現代において、果たして松下幸之助が経営理念に託した想いを継承することはできるのだろうか。Instagram、リプトン、ロレアルなど誰もが一度は名前を耳にしたことのある企業やブランドを渡り歩き、日本事業の責任者などの要職を務めてきた希代のマーケターである長瀬次英さんをゲストに迎え、100年存続するオーセンティックなブランドをつくるヒントやマーケティングの真髄とは何かについて語り合った。
前編はこちら

本質から導いたKPIには強い説得力がある(長瀬)
茂田正和:僕が長瀬さんからセンスのよさを感じたのは、組織運営におけるKPIの話を聞いたときです。ものすごく独特なKPI設定をしていますよね。
長瀬次英:そうですか?
茂田:ホテルや地方創生の旅館といった宿泊ビジネスの話がいい例です。親子三代が訪れて初めて1カウントと見なすKPIを設定していて、どうしたらそのような発想が出てくるのかと驚きました。
長瀬:人間の本質をKPIに設定しているんです。ノドが渇いたらみんな紅茶を飲む。だからリプトンのKPIは購入された数ではなく、紅茶がノドを通った回数なんです。じゃあ、飲まれた回数はいつわかるのかというと、買い替え時です。最初に買ったときはカウントせず、再購入時の個数から何杯飲んだかを割り出しカウントします。
宿泊ビジネスの話で言うと、設定したKPIは土地柄や気質と関係しています。とあるエリアでは代々母と娘が一緒に手をつないでデパートに出かける習慣があります。そうした層をターゲットにしたら必ずホテルの顧客として長い関係性が築けると考えました。三世代が通い続けるとなると100年ぐらいかかる計算なので、たしかにチャレンジングでしたが、本質から導いたKPIには強い説得力がある。僕からしたら人間の本質や行動心理をベースにKPIを設定しただけで、いつもそんな感じです。
茂田:僕は現在の香水市場の勢いにすごく危機感を感じています。国内市場は過去に類を見ないほど好調ですが、街を歩いていても香水をつける人が増えたような印象はまったくありません。おそらくきれいな瓶が家のどこかにいくつも並べられているだけで、香りを纏うという香水本来の役割とはかけ離れたものになっているのでしょう。
香水の利益構造は、使い続けてもらうことを前提に設計されていて、瓶を並べるだけで中身がいっこうに減らないとなると、従来の利益水準を維持した商品開発はできない。「これだけ世の中が盛り上がっているのだから、もっと香水を出してほしい」と求められても、「それは無理です」としか言いようがないんです。


——OSAJIは今春、記憶との結びつきをテーマにした新しいオードトワレを発売していますね。
茂田:今回僕らが出したオードトワレは、一般的な香水に比べて香りの立ち方が圧倒的に弱いのが特徴です。昨日まで香水をつけていなかった人が香水をつけてオフィスに行ったときに、「あれっ、香水つけているの?」と指摘されるのって意外にしんどいじゃないですか。それだと純粋に香水を楽しめないと思い、つけている本人は香りを楽しみながら、周囲にはそのことを悟られないギリギリの香りというのを狙ってつくりました。
やっぱり香水はつけるためにあるべきです。しかも、自分のために使うという。人とものとの本質的な関係に基づいてKPIを設定するべきという長瀬さんの話を聞いて、まさにその通りだなと思いました。あとは正しいKPIを設定し、運用していくための資金的な支えがあるかどうかが重要になってくるのでしょう。
長瀬:そこはすごく重要な点です。
茂田:三世代にわたって宿泊実績が確認できるまでに100年かかるとして、その間の資金が確保できなければKPI自体が絵に描いた餅になってしまいます。マーケティングの話をしていても最後は財務の話題になるように、経営に携わる者は常にファイナンスのことを意識して発想しないといけないでしょう。

写真を見せられて満足してしまったらマスターベーションの域を超えない(長瀬)
——長瀬さんが日本における最初の事業責任者を務めたInstagramは当初、写真を通して視野を広げ、新たな交流を育むことをサービスの本質に位置づけていました。でもいまは、ユーザーの興味・関心に基づいて情報を配信するプラットフォームの色彩が強く、当初掲げた理念とはだいぶ異なるものになっている気がします。
長瀬:僕がいまのInstagramを嫌う理由もそこで、広告収入をベースに開発されたアルゴリズムが優秀すぎるんです。ラーメンの写真ばかり投稿したり見ていたりすると、ラーメンのCMや情報ばかりが流れてきます。本来は、世の中にはもっと美味しいものがたくさんあるということを見せないといけないのに。視野を広げるのと狭めるののどちらかといえば、いまのInstagramは確実に後者でしょう。
ただし、頭の良い子たちはInstagramの性質を理解したうえでいくつものアカウントを使い分けています。おじさんの嗜好を知りたい人は、おじさんたちが好きそうなものすべてに「like」をし、アルゴリズムにおじさんのアカウントだと勘違いさせて関連情報を取得している。物は使いようと言いますが、そうやって使ったところで視野を広げる役に立つかは疑問です。
写真を見せられて満足してしまったらマスターベーションの域を超えないでしょう。好奇心と行動。そこをつないで、次のアクションを起こさせないかぎり、ブランドとの正しく関係はつくれないし、正しいKPIが生まれることもないんです。
茂田:いまのInstagramは検索した内容に基づいて一方的に情報を送ってくる、プル型のなりをしたプッシュ型ですからね。そうやってどんどん人の興味や関心を狭めていく。そこが罪深いと思います。
長瀬:罪は深いですね。

やるべきことをいかに短時間で効率よく処理し、やりたいことに時間を費やすか。人間はそうやって進化してきた(茂田)
茂田:僕は最近、いかに偶然というものを大切にして生きるかをテーマにしています。それは、偶然からしかロマンチックは生まれないからです。
長瀬:今日僕はここに来る途中、最寄り駅で「町中華」というワードで検索をしました。そうしたらラーメン二郎が表示されたのですが、店名以上の情報は探らないようにしました。なぜかというと、まさにいま茂田さんが話したロマンチックが欲しいからです。ラーメン二郎に行ったら休みだったんですが、その先にある別のお店で美味しいラーメンがいただけた。もし二郎の定休日を知っていたら、そのラーメンは食べられなかったかもしれません。こういう偶然の出会い、マジカルモーメントをいかに手繰り寄せるかがセンスの見せどころでしょう。そうやって新たな関係値をつくり、一緒に新しいことをクリエイションしていく。いまここでラーメンの話をしている時点で、そのお店との関係性がより深まったように思います。

——長瀬さんはデジタルの価値をどう捉えていますか?
長瀬:アナログやリアルな体験をより豊かで意味のあるものにしてくれることだと思っています。デジタルという存在があることで、人間本来の生き方が何であるかを改めて気づかせてくれる。それに気づいて行動した人たちだけが本当に無駄のない意味のある人生を送れるのでしょう。デジタルそのものにはそれほど価値はないですが、デジタルをうまく活用して、リアルで本質的な価値を楽しめばいいんです。
茂田:僕はスタッフに、やりたいことをやるためには、やらなきゃいけないことをどれだけ短時間で終わらせるかが重要だと言ってきました。時間は誰にでも平等です。そのなかでやるべきことをいかに短時間で効率よく処理し、やりたいことに時間を費やすか。人間はそうやって進化してきた生き物です。僕は家に帰ってもやらなくてはいけないことが終わるまで本も読まないし、映画も観ません。
でも、もしデジタルを使ってやらなくてはいけないことを効率的に終わらすことができたらそれはすごくありがたい。いまはアプリからボタンひとつでタクシーを呼べるので、配車センターにわざわざ電話をかけて待つ煩わしさがなくなりました。待ち時間がなくなったことで何通ものメールに返信ができたとしたら、それは間違いなくデジタルの恩恵でしょう。それなのに、世の中には未だに「デジタルばかり使っていたら頭が悪くなる」と言うデジタルアレルギーな人がいます。子どもがデジタルに依存しようとすればするほど、「そんなものに頼っていてはダメだ」と言う親も少なくない。それぞれの価値観がうまく共存できたら、デジタルは純粋に便利なツールとして多くの恩恵をもたらす気がします。

競争社会では日本人の本領は発揮されにくいのかもしれない(長瀬)
茂田:僕らが手がけるOSAJIというブランドは、「わびさび」がひとつの重要なテーマです。ただ、この言葉を理解するのは容易ではありません。レナード・コーエンが書いた本なども読んで勉強しましたが、それでも自分のなかできちんと説明できる感覚がなかなか湧きませんでした。でも最近、「わびさびとはセンチメンタルだ」と気づいた瞬間にすごく腹落ちしたんです。センチメンタルやセンチメンタリズムって、日本人がいちばん得意とする部分で、世界の関心もいまそういう方向に向かっているように思います。
前回、写真家の蓮井幹生さんと対談をしたときに、「朽ちていくとか、老いていくことに対してエモーションを感じるのは日本人ぐらいだ」という蓮井さんの発言がすごく印象に残りました。言われてみたら、陰影なんかに魅力を感じるのもすごく日本的だといえます。わびさびの正体がセンチメンタルだと思えた瞬間に、この言葉に対する解像度が一気に上がった気がしました。
——先ほど挙がったロマンチックというワードにも、センチメンタル的な要素があるように思います。
茂田:究極を言えば、ロマンチックとはセンチメンタルのことであり、その逆もしかりのような気がします。ふたつの言葉は最近僕のなかですごく重要なキーワードです。そしてその正体が「わびさび」です。
先日テレビ番組を見て思ったのですが、スティーブ・ジョブズがなぜあれほどまでに日本の美意識に惹かれたのかを紐解いていくと、センチメンタリズムみたいなものに行き着くんです。世界中の人が最も優れたユーザーインターフェースだと認識しているiPhoneは、そうしたジョブズの想いから生まれたプロダクトで、ゆえに日本人との親和性も高い。創業100年を超える企業の半分が日本の会社なのも、実は理性や思考よりも感情に左右されやすいという日本人のセンチメンタルな感覚が大きく影響しているように思います。

——ブランドづくりの話にセンチメンタルというキーワードを当てはめると、どういうことが言えそうですか?
長瀬:センチメンタルってものすごく心に残るので、そこじゃないでしょうか。その連続があって初めてブランドは存続できる。そういうセンチメンタルな旅、「センチメンタル・ジャーニー」を続けていくことがブランドづくりにも人生にも大切です。
茂田:昨日読んでいた本にこんなことが書いてありました。バブル崩壊後の30年を日本人は「空白の30年」と言ってきましたが、海外の人たちは日本が次に飛躍するための準備期間だと位置づけていると。言われてみると何となくそんな気がしてきました。じゃあ次に日本が目指すべきは何かといえば、「究極的に美しいガラパゴスにいかになれるか」だと思っています。もちろん、そこに辿り着くにはかなりの要件整理が必要になるでしょう。

——どういうものが不要だと?
茂田:いちばんは「競争」です。そもそも日本人の宗教思想に「競い合う」という考え方はないんです。人と比較しないことが禅の基本ですから。そんな日本人にとってグローバル競争というものがいちばん余計だったと僕は思っています。もっとガラパゴスでよかったのではないかと。
競争の結果として経済が循環していることを考えると、再びガラパゴスに戻るのはなかなか難しいかもしれません。でも、先端テクノロジーの分野でも遅れをとる日本はそろそろ競争の土俵から降りて、美しいガラパゴスを目指したほうがいい。それが日本の次のゴールだと思っています。
長瀬:その流れはたしかにあります。教育でも人と競うのではなく、個を尊重する方向にシフトしていますから。競争社会では日本人の本領は発揮されにくいのかもしれないですね。
茂田:人と競争するぐらいなら、友だちをたくさんつくったほうがいいんです。
長瀬:最後は友だちの話に戻りましたね。
茂田:いろいろと参考になりました。ありがとうございます。

Profile
-
長瀬次英(ながせ・つぐひで)
1976年京都生まれ。中央大学総合政策学部国際政策文化学科を卒業後、2000年KDD(現・KDDI)に入社。J. W トンプソン、ユニリーバ・ジャパンなどを経て、フェイスブック・ジャパンに入社。マネタイズ事業の立ち上げや事業の拡大に貢献する。2014年にInstagramの初代日本事業責任者を務める。その後、ロレアル日本法人初代CDO(最高デジタル責任者)、LDH JAPAN執行役員兼CDOなどを歴任。2019年以降は複数企業の顧問としてパラレルワーキングを実践し、現在に至る。著書に「マーケティング・ビッグバン インフルエンスは『熱量』で起こす」(CCCメディアハウス)、「能ある鷹もない鷹も爪は隠さず研ぎまくれ」(ことのは出版)、「今日の君への言葉 直感が導くビジネスメッセージ」(太陽文庫)などがある。
-
茂田正和
音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ。04年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業ヘルスケア事業として多数の化粧品ブランドを手がける。17年、スキンケアライフスタイルブランド「OSAJI」を創立しブランドディレクターに就任。21年にはOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香-」(東京・蔵前)、22年にはOSAJI、kako、レストラン「enso」による複合ショップ(神奈川・鎌倉)をプロデュース。23年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド「HEGE」を仕掛ける。同年10月、株式会社OSAJI 代表取締役CEOに就任。著書に『食べる美容』(主婦と生活社)、『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)があり、美容の原点である食にフォーカスした料理教室やフードイベントなども開催。24年11月にはF.I.B JOURNALとのコラボレーションアルバム「現象 hyphenated」をリリースするなど、活動の幅をひろげている。
Information
著書
「マーケティング・ビッグバン インフルエンスは「熱量」で起こす」
マーケティングの原点は人の心を動かす「熱量」だという長瀬さんがコロナ禍に執筆した初の著書。Instagramの初代日本事業責任者、日本ロレアルやLDH JAPANでCDOを務めた自身の経験を踏まえ、ビジネス環境がいかに変わろうともマーケティングにおいては高い熱量を携えて現場に足を運ぶこと、顧客に直接聞くこと、人に会って話すことが重要であることを説く。巻末には長瀬さんの個人宛連絡先が掲載され、読んだ人が直接感想を伝えられるようにもなっている。
「今日の君への言葉 直感が導くビジネスメッセージ」
働く人を応援する108の言葉を収めた長瀬さんの著書。読者に語りかけるように綴られた詩のような文章が、ビジネスパーソンに限らず多くの読者の心の支えとなり、行動を後押しするはずだ。パラパラとページをめくりながら、気になったワードから読み進めるのに最適な一冊でもある。文章に添えられた印象的なイラストはメイクアップアーティストのTAKAKOさんが担当する。
-
写真:小松原英介
-
文:上條昌宏
NEWS LETTER
理想論 最新記事の
更新情報をお届けします
ご登録はこちら
ご登録はこちら
メールアドレス
ご登録ありがとうございます。
ご登録確認メールをお送りいたします。