
2025-05-01
Vol.16
フライングサーカス代表、ジンフェスティバル東京主宰
三浦武明 氏(後編)
-
ニーズを聞いてはいけない
-
無口な自分が顔を出すとき
-
感覚は科学を超える
-
神道とイスラム
訪れたのは渋谷駅から徒歩10分ぐらいのところにある迷路のようなビルの一角。店内に入ると、そこで待ち受けていたのは1,000本以上のジンのボトルと今回のゲストである三浦武明さんだ。日本におけるクラフトジンの第一人者として知られる三浦さんは、飲食店オーナーや蒸留家などいくつもの顔を持つ。OSAJIブランドファウンダーの茂田正和とは、2020年末に誕生した「YOHAKHU」というクラフトジンづくりをきっかけに知り合い、いまでは互いを「親友」と呼び合う間柄だという。
共に、音楽、文化、香りへの関心が高く、ストリートが面白かった90年代カルチャーを体現するふたりが、ロマンチック、神道、イスラムなど多岐にわたるテーマについて意見を交わした。
前編はこちら

手土産を持っていったときに、その人が知っているものを渡したら負け(茂田)
茂田正和:僕はものづくりをするときに常に自分に言い聞かせていることがあって、それは「ニーズを聞いてはいけない」ということです。ニーズに応えようとすると、結局は必然を提供するだけになってしまう。僕らが本来やらなくてはいけないのは、潜在化している欲求を探りにいく作業です。それをスタッフにもずっと言い続けてきました。
——どうすれば人の潜在欲求を見つけることができるのでしょう。
茂田:僕は人に何かをプレゼントすることがすごく好きで、そこで感覚を磨くトレーニングをしています。相手の行動や動きを観察し、何であればまだ見たこともない衝撃的な出会いを提供できるかを考えるんです。手土産を持っていったときに、その人が知っているものや気になっているものを渡したら負けです。「こんなのがあるんですね、初めて知りました」と言われてはじめて、プレゼントを贈ることの喜びや意味を見出すことができると考えています。
うちの会社が「基本マーケティングリサーチはしません」と言っているのは、マーケティングリサーチは顕在化されたニーズしかあぶり出せないからです。そもそも顕在化しているニーズはリサーチをしなくてもわかります。顕在化したニーズに答える仕事は僕らよりもお金をかけて大規模にマーケティングリサーチができる人たちに任せておけばいい。僕らはそれよりも、「こんなものもあるんですね!」と思ってもらえるようなものをつくりたいんです。
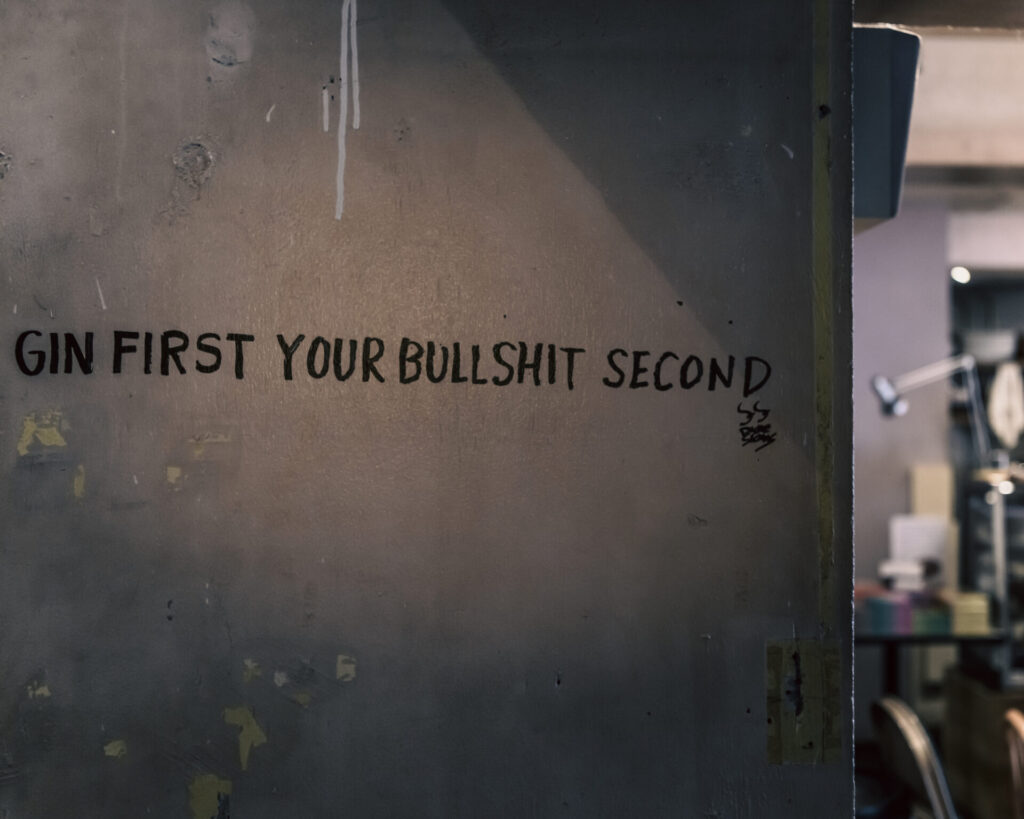
ただし、そうやってつくったもののなかにはまったく売れなくて、ひどい火傷を負ったものもあります。スタッフから詰められて、しんどい思いをしたのも一度や二度じゃない。でも、やっぱり心が動く瞬間というのは偶然のなかにしかなく、そういう出会いに遭遇するために所作も含めていろいろ精進する必要があるでしょう。この年齢になると自分が欲しくなくても変な貫禄がついてしまいます。それによって若い子たちが気軽に声をかけづらくなっていたとしたら、危機的な状況です。だから、脇を甘くし、いかにつけいる隙を用意するかがいまの僕の課題です。
三浦武明:とても茂田さんらしい話ですね。自分はむしろ極端なぐらい偶然しか信じていません。そして、余計なノイズを減らしていけば必ず素敵な偶然の出会いにたどり着けると信じています。もしそういう機会が減っていると感じたら、情報に惑わされて自分らしい判断ができていないと思うようにしています。茂田さんとの出会いも、単純にうれしいという以上に、この人はこれから先自分に何をもたらしてくれるかという関心のほうが大きかった。偶然の出会いが自分を試しているような気がしています。

落書きからは言葉にならない悲鳴のようなものが聞こえてくる(三浦)
三浦:お店って合法的な落書きのような存在でもあると思うんです。自分がやっているお店は特にそうです。公共の壁に落書きをしたら怒られるけれど、お店というかたちでなら街に存在できるしわがままが許されます。
毎日青山トンネルを通るんですが、落書きをされては消されるという繰り返しの光景を見ていて、都市というのは経済成長の過程で落書きと野良犬を排除していくのだと思ったんです。野良犬は確かにあまりいないほうがいいけれど、落書きからは言葉にならない悲鳴のようなものが聞こえてくるような気がしていて。そういうものがどんどん街から消されていくのはどうなのだろうと考えていた矢先に自分の店の看板に落書きをされました。でも、色づかいもデザインのセンスもなかなかよかったので、思わず「ふ〜ん、やるじゃん!」と(笑)。その落書きは消さずに残しています。
——三浦さんはいまもお店に毎日出られているのでしょうか?
三浦:カフェを手がけていたときから接客をずっとやってきました。すごくおしゃべりだったので、性に合っていたのでしょう。いまも現場には入りますが、レギュラーで接客をするのは10年前にやめました。ただし、やめた途端にものすごくストレスを感じるようになって。原因は、毎日何万語としゃべっていた言葉数が一気に減ったことです。そのときはじめて、自分の接客はお客さんの話を聞くのではなく、自分のことをひたすら話していたのだと気づき、恥ずかしくなりました。
一度すごく体調が悪いときに、現場の人手が足りなくて接客に入ったときがありました。明らかにいつもよりテンションが低いし、言葉数も少ない。お客さんに心配されたらどうしようと考えていたら、二組のお客さんから「武さん、今日は感じいいですね」と言われて。やっぱり普段しゃべりすぎだったのでしょうね(笑)。

——コロナ禍ではかなり長くお店の休業を余儀なくされたはずです。お客さんとの接点がなくなり、会話することが叶わなかった時期も相当なストレスを感じたのではないですか?
三浦:イエスとも言えるし、ノーとも言えます。ちょうどその頃、自分の蒸留所を立ち上げる計画を進めていて、社交的ですごくおしゃべりな自分とは違う、すごく無口な三浦武明が顔を出していたんです。ギターを弾いているときもそうですが、自分自身と対話をしているようなときはしゃべらないことがストレスになりません。蒸留所のプロジェクトにとりかかって、久しぶりにそういう自分が出てきたように感じました。いまはお店でやってきた場所づくりより、ものづくりに本気で取り組みたい気持ちが高まっていて、そういうモードに入ったときはけっこう無口です。茂田さんもわりと喋るのが好きなほうですが、無口なときってありますか?
茂田:武さんと話しているときは無口です。武さんがよくしゃべるから(笑)。あとは料理をつくっているとき、文章を書いているとき、香りの調香をしているときです。
実は僕も最近、いずれ経営者という立場から離れて、ものづくりに専念したいと思うことが増えてきました。でも、絶対にそうしたいと思っているわけではなく、ライフワークから経営という要素を外したときに、残ったものでどう自分の色を変えていけるか、そこにワクワクするような期待を抱いています。

——経営という仕事にワクワクするような思いをはせるのは難しいのでしょうか?
茂田:経営という行為自体が楽しいというより、経営を通じて遊び場のようなものがつくれたら楽しいだろうなと思っています。会社という組織やブランドも同じで、そこに集う人たちが「あそこの公園がいちばん楽しいよね」と思えるような場をつくりたいのです。もちろん遊び方のセンスは問いますが。武さんが手がけるお店にも似たような雰囲気を感じます。
——三浦さんが主宰するジンフェスティバル東京は、すごくそういうものに近いと思います。
三浦:お店で出しているボトルの生産者は全員が個性的で味わい深い人たちです。だったら、その人たちのことを自分が話すより、直接会ったほうがぜったいに楽しいと思って始めたのがジンフェスティバル東京です。フェスでの出会いが刺激となり、友だち関係に発展し、そこから新しいカルチャーが生まれていってほしいという一種の種まきです。もちろん、自分が楽しみたいという思いも含めてですが。そういう意味で、遊び場をつくろうという感覚がどこかにあったのかもしれないですね。

とるに足らない日々の些細な出来事を丁寧に凝縮し、届けたい(三浦)
三浦:茂田さんという人は、現状に満足せず、「もっとこんなこともできる」という思いが人一倍強いのだと、今日、改めて感じました。そうした感情はどこから生まれてくるんですか?
茂田:貪欲なだけです。もっと上には上の快楽があるだろうと。周りからは人を喜ばせるためにやっていると思われますが、実際は自己満足。でも、最後には自己満足でやったことをきっと誰かが喜んでくれると思っていて。それが気持ちよくもあり、やり続けられる理由のような気がします。あの人とこの人を引き合わせたら面白い化学反応が起こるんじゃないか、そんなことを考えるのも利己的な動機です。
見たことのない景色をもっと見てみたいという欲求は、海外旅行をする感覚と近いかもしれません。あの国に行ったら人生観が変わったという経験は誰にでもあるはずです。僕も昨年、45歳にして初めてヨーロッパに行ってそんな経験をしました。
三浦:意外ですね。
茂田:それまでアジアには取り憑かれたように行っていましたが、ヨーロッパにはなかなか興味が持てなかったんです。でもミラノに行ってみて、「ヨーロッパって面白いじゃん!」と。長い歴史が紡いできた痕跡がいろんなところから見えることはすごいなと思えて、人生観が変わりました。同時に、もっと違う景色を見てみたいという気持ちが高まった感じです。

——三浦さんはジンというお酒を介して世界やローカルの動きを肌で感じているのではないでしょうか?
三浦:TOKYO FAMILY RESTAURANTは食を通じて世界を知ることをコンセプトにしていますが、お店を始めた当初、自分のなかには「Think globally, act locally(地球規模で考え、地域で行動する)」という思いが強くありました。でもジンは逆で、「Think locally, act globally(地域で考え、地球規模で行動する)」という感じで、ジンを通じて世界とつながっていくイメージです。
お店とジンのプロジェクトは自分にとって二部作のようなもので、両方を手がけることで初めて思いがかたちになる気がするんです。一昔前は、規模を大きくしないと遠くに行けないとか、早く動きたかったら小さいほうがいいと言われましたが、時代が変わり、小さくても遠くに想いを届けることができるようになりました。そしていまは、とるに足らない日々の些細な出来事を丁寧に凝縮し、届けたいという思いが強くなっています。そういうことをやるには、むしろ小さい規模のほうが適している気がします。

茂田:前々回の理想論で医師であり山形ビエンナーレの芸術監督を務めた稲葉俊郎さんと対談したのですが、そのときに非科学と未科学という話題になりました。稲葉さんは非科学という言葉を使わず未科学と呼ぶようにしていて、理由を尋ねると、「非」という否定的なニュアンスからは何も生まれないからだと言われたんです。その話を聞いて、僕はすごくロマンチックだなと思いました。
多くの人は見えていないものはいらない、そんなものに何の価値があるのかと否定的な捉え方をします。でも、見えていなかったり、聞こえていないようなものにも心が動く瞬間がある。理論的に説明はできないですが、そういうものが未科学的だったりするのではないでしょうか。街で武さんと偶然ばったり出会う機会が多いのも、僕は未科学のような気がするのです。
三浦:自分たちが認識し、感じたことを具体的な言葉に変換できているものはゼロコンマ数パーセントでしかないという感覚があります。感覚と言うと馬鹿にされそうですが、自分にとっては科学より上で、圧倒的に信頼できる。50歳になって、その確信がより深まったように思います。ただ、これは科学を否定する話ではなく、むしろ未科学というものに対する解釈の仕方なのかもしれません。未科学という言葉を自分は茂田さんから聞くまで知りませんでしたが、そういうものに対する感度というのは誰もが潜在的に持っているものでしょう。

この国の思想の隅々には自然現象を神と捉える考え方が息づいている(茂田)
茂田:日本には「いただきます」という言葉があります。食事をする前に命をいただくことに感謝の気持ちを表すのは、日本人だけだと言われています。そこには、何事にも神や命が宿っていて、それを分かち合って自分たちは生きているという考えが反映されています。その考え自体が、未科学的な思想のような気がします。この国は基本的に無宗教ですが、思想の隅々にそうした自然現象を神と捉える考え方が息づいています。いま世界が日本に注目していますが、その一方で、逆に日本人がその価値に気づかなくなっている気がします。
三浦:自然の力を神々の働きとして捉える考えは神道に通じていて、日本で独自に発展した宗教としてすごく面白いと感じています。神道には、開祖、教祖が存在せず、経典もない。にもかかわらず日本人の生活に大きな影響を与えて続けている。教祖や経典がないから誰も奪えないという点でも究極の知恵だと思います。
この前NHKで日本のマンガが世界を席巻しているという番組を見ていたのですが、マンガというのはいま、世界中のマイノリティの感情を支えているものとして機能していると感じたんです。そこにはおそらく神道的な価値観がこっそり埋め込まれていて、マンガに接することで世界中の人たちが救われているのでしょう。そうやって、日本人が宿してきた神道的な価値観、いただきます的な世界観がじわじわと世界に広がっているのだとしたら、それはすごいことだと番組を見て感じました。

茂田:最後に、武さんにどうしても聞きたかったことがあります。なぜ自分のつくったジンに「オリエンタリア*」という名前を付けたのか? その理由を教えてください。
三浦:これは少し長い話になります。大航海時代、東インド会社によってイギリスやオランダにもたらされた香辛料、その魅惑的な香りはジンというお酒の誕生に欠かせないものとなりました。そして日本へは、香りの文化は仏教を通じてもたらされ、やがて香道として独自に発展していきます。壮大なシルクロード、ユーラシア大陸の東端である日本への香りの旅が、自分のジンづくりのテーマでした。
途中で「オリエンタリア」という名前を思いつくのですが、そのきっかけは10代のときにイスラム史を学ぶために手にした、パレスチナ系アメリカ人であるエドワード・サイードの「オリエンタリズム」という本です。他者や異文化を理解するうえでの前提であったり、そもそもこれまでのイスラム史はあくまで西洋からの目線や都合で語られてきたものであるという視点は、その後の自分の人生や価値観に大きな影響を与えました。
最初はそのまま「オリエンタリズム」と名付けようと思ったのですが、それがオリエンタリアになったのは、大好きなブラジル人アーティストのカエターノ・ヴェローゾらが1960年代に提唱した「トロピカリア運動」からのインスピレーションです。文化や芸術を通じて美しきアジアの伝統や価値を再定義する、オリエンタリア・ムーブメントという意味も込めてこの名前に決めました。日本はもちろんアジアをローカルと捉え、自分らしく世界へ発信していきたいと思っています。

——アジアの香りの文化に思いをはせてつくられたものだったのですね。
三浦:実はこの話には続きがあります。年始に親父が亡くなり、喪主として葬儀に参列したときに、棺桶にぶちまけようと持参したオリエンタリアのボトルを見て、隣に座っていた親戚のおじいちゃんが名前の由来を聞いてきました。母いわく、その人は日本におけるイスラム研究の第一人者で、経緯について話すと、「あの本を読んだのか?」と尋ねてきました。何でそんなことを聞くのかと思ったら、その人が研究者になる前に勤めていた出版社で最後に企画した本がそのオリエンタリズムだったんです。確かにあとがきにも記名の文章が載っていました。まさに今日の話ではないですが、いろんな偶然が重なっていたんです。本当はこの話を親父に聞かせたかった。でも、親父が亡くなったからこそ聞けた話でもあり、最後に親父が引き合わせてくれたのかなと思っています。
10代でイスラムの文化に心が動いたことが、後々このようにつながっていくとは当時は想像もしていませんでした。でも、時々こうした偶然の出会いが大きなものをもたらしてくれることがあります。それによってどこにたどり着き、どんな風景が見られるのかを楽しみにしている自分がいます。会社やお店、家族のことなどいろんな責任を背負う立場ですが、それでも心が動くことを常に最優先事項にしていて、これからもそれは変えようがないと思っています。

——飲食店が醸す雰囲気は、料理、サービス、スタッフの応対などあらゆる要素が混ざり合ってできあがるものであり、ひとりのオーナーの考えや行動だけでは生み出せないと思っています。三浦さんはどうやってスタッフと考えを共有していますか?
三浦:意図的に考えをすり合わせるようなことはやっていません。むしろ、合わせない。経営者としてはダメなのでしょうが、人を評価したり、教育したりするのが好きではないんです。
人って楽しかったらやるし、ワクワクすれば動きます。でも逆に、「何かをやらなくちゃいけない」「何か行動しなくちゃいけない」となると、強迫観念に駆られて動けなくなる人もいる。そういう人の成長を邪魔している要素を本人に気づかれないようちょきちょきと切ってあげる。自分がスタッフに対してやっているのはそれぐらいです。自分のDNAをスタッフに受け継いでもらいたいとはいっさい思いません。仲間として自分の言葉を話せる人であって欲しいし、「勝手にやってくれ」という感じです。
茂田:今日はものすごく魂のこもった話を聞かせてもらえた気がします。ありがとうございました。
三浦:最近イベントで会っても、「よっ!」みたいな感じで終わっていたので、
じっくり話ができてうれしかったです。

*オリエンタリア
Disttiler M初の作品。重奏的な香りのレイヤーと長く続く余韻。香木や墨汁といった和のテイストを感じさせつつも、全体として灼熱や大地のニュアンスといったアジアらしい香りが際立つ。東京下町のガラス瓶メーカーに特注したオリジナルボトルや、ボトルにプリントした「orientalia」の文字は、すべてひとつずつ手作業でつくられる。2025年5月中の再販を予定している。
https://distiller-m.com
Profile
-
三浦武明(みうら・たけあき)
1974年東京都生まれ。株式会社フライングサーカス代表取締役、ジンフェスティバル東京
主宰。90年代より飲食店プロデュースに携わり、2000年初頭のカフェブームを牽引。その後、直営店のTOKYO FAMILY RESTAURANTなど都内を中心に30店舗以上の飲食店や商業施設の立ち上げ、イベントや催事等の企画・実施を行う。21年に”Gin is Music”をコンセプトに、香りと音の探求をするジンブランド「Distiller M(ディスティラーエム)」をスタート。24年7月に蒸溜所初のオリジナルジン「オリエンタリア」をリリース。京都の老舗生麩店「麩嘉(ふうか)」と組んで蒸留酒づくりなども行っている。 -
茂田正和
音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ。04年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業ヘルスケア事業として多数の化粧品ブランドを手がける。17年、スキンケアライフスタイルブランド「OSAJI」を創立しブランドディレクターに就任。21年にはOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店「kako-家香-」(東京・蔵前)、22年にはOSAJI、kako、レストラン「enso」による複合ショップ(神奈川・鎌倉)をプロデュース。23年、日東電化工業の技術を活かした器ブランド「HEGE」を仕掛ける。同年10月、株式会社OSAJI 代表取締役CEOに就任。著書に『食べる美容』(主婦と生活社)、『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』(宝島社)があり、美容の原点である食にフォーカスした料理教室やフードイベントなども開催。24年11月にはF.I.B JOURNALとのコラボレーションアルバム「現象 hyphenated」をリリースするなど、活動の幅をひろげている。
Information
TOKYO FAMILY RESTAURANT
2006年渋谷区東にオープンした「食で世界を旅する」をコンセプトにした“東京のファミレス”。異国情緒たっぷりの空間で、世界30カ国以上の料理とクラフトジンやビールが楽しめる。営業は月〜金の週5日、いずれもランチタイムから18時まで。また、日本最大級のラインナップを誇るジン専門のボトルショップや、三浦さんが自ら設計したオリジナル蒸留器を置くジンの蒸溜所「Disttiler M(ディスティラーエム)」も併設する。
Instagam:@tokyofamilyrestaurant
ジンフェスティバル東京
2018年にスタートしたアジア最大級のジンの祭典。情熱を注ぐ造り手やインポーターが集い、ジンの魅力を発信するとともに、ジンを介した新たなつながりから、ジン文化のさらなる発展を見据える。コロナ禍の休止期間を経て5年振りの開催となった24年は、国内外から80社、過去最高100ブランドが会場に集結した。次回は26年の開催を予定している。
Instagam:@gin.festival_tokyo
-
写真:小松原英介
-
文:上條昌宏
NEWS LETTER
理想論 最新記事の
更新情報をお届けします
ご登録はこちら
ご登録はこちら
メールアドレス
ご登録ありがとうございます。
ご登録確認メールをお送りいたします。


