
2023-12-16
Vol.1
MOTION GALLERY 代表
大高健志 氏
-
多様性とデモクラシー
-
クラウドファンディングは創造表現
-
個人が発信するジャーナリズムの可能性
-
未来は「社会彫刻」からつくられる
多様な価値観の必要性が叫ばれる一方で、SNSの普及などもあり社会における同調圧力はいっそうの高まりを見せている。そんな現状を打破するために必要なこととは何か? クラウドファンディングのプラットフォーム、MOTION GALLERY(モーションギャラリー)を運営し、それ以外の事業としても映画のプロデュースから劇場公開まで幅広く支援する大高健志さんをゲストに招き、クラウドファンディングとミニシアターを掛け合わせた映画文化の創造や個人ジャーナリズムの可能性などについて語り合った。

多様性の根源となる思想を大切にしないと、いつまでたっても豊かにならない(茂田)
茂田正和:この国で多様性が認められるようになったのって、おそらくバブル崩壊後だと思うんです。ちょうどその頃からセカンドプレイヤーやサードプレイヤーが活躍しだし、メイン通りから1本裏に入った路地に構える店が盛り上がりはじめた。
大高健志:裏原とか、確かにそうですね。
茂田:その後ITバブルの崩壊が起こるんですが、これは文化にとってものすごい脅威となったんです。崩壊のスピードがバブルと比べて桁違いに早かったので、それまで10年とか15年のスパンで投資回収をしていた人たちが、「そんなに悠長に構えていたら大火傷をする」と言い出し、回収までのスパンを3年とか5年に一気に縮めてしまった。短期回収するために投資会社は何をするかといえば、マーケティングへの集中投資です。無尽蔵に費用を投下し、一気にユーザー数やブランドの認知度を高める。その結果何が起きるかというと、ブランドの大衆化なんです。コアなファンが急速に離れ、誰が支持しているのかわからないブランドとなり、古びた暖簾だけが残るという事態がいたるところで起こったんです。
文明がなぜ滅びるかについて以前に環境モニタリングをしている方に話を聞いたんですが、いちばんの理由は森の多様性が喪失され災害が起こることなんだそうです。雑草が生え、低木や巨木があって、そこにさまざまな動物が息づくことで、多様な環境ができあがる。にもかかわらず経済合理性の観点で、雑草や低木には目もくれず木にだけ投資をすると自然環境の多様性は失われ、洪水や土砂崩れ、山火事の引き金になりかねないんです。
ビジネスにおいてもそうだけれど、近視眼的な視点で集中投資をすることって多様性を奪うことに他ならないんです。プラネタリウムに公的な予算を充てるなら、僕は多様な思想や感性を育むミニシアターにも予算を割くべきだと思う。多様性の根源となる思想の部分を大切にしないと、社会の多様性なんて絶対実現しないし、そういう国はいつまでたっても豊かにならないですよ。
大高:映画に関して言えば、ミニシアターの存在こそが多様性の源泉というのは間違いないんです。多くのスクリーンを備え、大量の人を動員する前提でつくられたシネコンではその役割は果たせないでしょう。一時、すべてのスクリーンで同じ作品を上映するということがありましたよね。利益優先だとそういう動き方になるんです。でも、ワンスクリーンの規模で運営されるミニシアターではそういう手法はとれないし、そもそもシネコンで何スクリーンも使って上映されるような作品は回ってきません。それをポジティブに捉えれば、興行収入云々ではなく、「10年後にこの監督は世界的な名声を獲得するから今のうちに見てほしい」といった、将来性を見越した思い切ったラインナップが組めるのはミニシアターぐらいしかない。そこにシネコンとは違った存在意義があると思っています。

——映画における多様性とは?
大高:人によっては監督の作家性かもしれないし、描かれているテーマかもしれません。未知なる発見を求めることだったり、実験的な映像に多様性を見出す人もいるでしょう。要は、原作が有名で、人気のある俳優を揃えましたみたいなわかりやすい勝利の方程式から外れたもの、あるいはそんなことを意識させないものです。また、そういう作品を観たいと思ったときに、観る機会がきちんと用意されているというのも、映画におけるひとつの多様性だと思っています。
——大高さんも自身でミニシアターを運営していますが、近年のミニシアターの状況というのは?
大高:どこもコロナ前と今とを比較すると軒並み10パーセント以上観客数が落ち込んでいます。東京に限ればそこまで減っている印象はないですが、地方は本当にお客さんが入らないと聞いています。生活に直結しないようなアートへの関心が薄れているかもしれません。
茂田:コロナ禍が助長したもののひとつに、都心部と地方との文化格差があったと思うんです。東京や大阪に気軽に行けない時期があって、地方の人たちはインスタなどのSNSを通じて都心で起こっていることの情報に触れていた。でも、そこで得られる情報はかなり集約化されたもので、しかもインタレストマッチやクッキーのようなアルゴリズムが裏で働いているから、自分の関心のある情報しか流れてこない。リアルにその場に行き、街をザッピングして歩いて偶然新しい何かに出くわすということがほとんどない2年間だったんです。
僕は群馬と東京の2拠点生活をしているけれど、文化格差はやばいと感じています。たまたま住んでいるのが映画祭の盛んな高崎なので、映画に対するリテラシーだけは異常に高いんですけど(笑)。でも、ショッピングモールで買い物をしている人が「シネマテークたかさき」のようなミニシアターで今どんな映画をやっているか、ほとんどの人は知らないでしょう。ショッピングモールに行く人たちが少し背伸びをして普段観ない映画を観ようと思わないかぎり、ミニシアターの集客は上がらないんじゃないかな。
——どうしたらそういう意識変革が生まれると?
茂田:僕はシンプルに「民主主義=多数決」ではない、ということを上に立つ人たちがきちんと理解し行動することだと思ってます。多数決の結果でものごとを判断するのは楽ですよ。民主主義は「私のことは私で決める」という考えが前提で、少数意見の人にとっても居心地のいい場所じゃなきゃいけない。そういう感覚を持って判断を下せるのが真のリーダーです。多数派の意見だけですべてを決める発想は、ショッピングモールに通う人たちだけが住みやすい社会をつくるのと同じ。それこそまさに多様性の喪失でしょう。少ないからといって全部なかったことにしてしまうのは、社会から多様性を奪うことに他ならないんです。
大高:多数決だけでものごとを決めないという指摘はその通りだと思います。それでも多数決がまかり通っているのは、誰もが自由意志で票を投じているという前提に立っているからなんです。でも本当にそうなのか? 選挙で風が吹くのと同じで、なんとなくみんながいいと言っているからこっちに入れようみたいな感覚で投票しているケースは意外に多いと思うんです。
クラウドファンディングが多数決と違うのは、美人投票ではない投票行動で自由に社会を上書きしていける機能を備えているからです。そして、再生回数やアクセス数といった数値には現れない「熱量」のようなものが個人の意志として大きく反映される。再生回数って、暇だからとりあえずかけておこうというのも1回にカウントされますよね。何百万回再生されたからすごいと言われているものも、実は熱量の低い低体温の積み重ねというケースがけっこう多かったりするはずなんです。対してクラウドファンディングはそういうものとは違ったカウンター機能を備えていると感じています。

クラウドファンディングは、クリエイション表現であり創作活動の手段(大高)
茂田:ここ数年僕のなかにある違和感があって、それはメーカーに対する環境対応への要求です。ものづくりの現場で対応しようとするとどうしてもコストが嵩むんです。だから「環境対応はしますが、現状よりも高い値段を払っていただけるんでしょうか?」と尋ねると、そうじゃないという話になる。
大高:メーカーの努力でなんとかしろという発想ですね。
茂田:多くの人がリサイクル品は安いと考えがちですが、実際はその逆で、回収して選別し、再加工して製品にするわけだから手間もコストもかかる。本気で環境にいいことをやろうと思ったら、元の売り値の1.5倍ぐらいじゃないと成り立たないでしょう。でも、その値段になったら、結局ちゃんと環境対応されてない安価な製品に流れてしまう。環境対応は全人類の問題なのに、こういう構造になってしまっていることが違和感なんです。
社会がいい方向に向かうには、つくる側の努力だけじゃだめで、使う人たちの協力が欠かせない。僕は佐賀にある「PICFA(ピクファ)」という障がい者施設の人たちと一緒にパッケージデザインの仕事もやってるんですが、彼らとの協働に対して支援という気持ちは1ミリもないんです。マンネリ化したデザインに風穴を開けたいから僕は彼らと組むし、彼らも僕とやることがひとつのモチベーションになる。そういうウィンウィンの関係じゃないといいものは生まれないし、社会を動かせないでしょう。
大高:クラウドファンディングも一緒です。お金を投じる行為は支援というよりも、ある種のクリエイションであり、表現であり創作活動の手段なんです。土下座して「出資してください」みたいなノリでクラウドファンディングをするのはちょっと違うし、「お金を出せばいいんでしょ」みたいなことでもない。こういうものをつくってもらいたい、こんなものがあってほしいという意志にお金を託す創造的な行為と捉えてほしいんです。そこがヨーゼフ・ボイスの提唱した「社会彫刻」という考えに近いと思っています。

茂田:僕は大高さんから「社会彫刻」という言葉を初めて教えてもらった。どういうきっかけでこの言葉を意識するようになったんですか?
大高:大学へ行くまでそれほどアートに興味はなかったんです。子どもの頃、テレビで岡本太郎が「芸術は爆発だ!」って叫んでいるのを見て、アートって意味わかんないし、変なものだから触れないほうがいいぐらいに思ってました(笑)。ただ、映画が好きだったので、映像文化評論系のゼミに入った流れで岡本太郎やアンドレアス・グルスキーの写真などに触れて、彼らのことをきちんと学ばなくてはという気持ちになっていったんです。岡本太郎の本を読むと、「芸術は爆発だ!」ということがロジカルに説明されていてびっくりしました。テレビではおちゃらけた感じで取り上げられていたけれど、実はひじょうに緻密な理論を展開する人なんだと。それ以降、他の現代アーティストにも興味を抱き、アート史を学ぶなかでボイスの存在を知り、「社会彫刻」という言葉に出会うんです。
アートの文脈ではあるけれど、同時に社会運動の視点からもひじょうに面白い考えだなと思いました。何をもって民主主義と言うのか、そのことを論じているような感もあって。もともと大学で政治哲学を専攻していたので、アートと政治哲学の双方をまたぐボイスの考えに惹かれるまでにそれほど時間はかかりませんでしたね。

個人ジャーナリズムが何かの圧力で歪められるようなことがあってはいけない(茂田)
茂田:僕は今の時代、個人ジャーナリズムみたいなものがすごく大事だと思っているんです。そのベースとなるのは間違いないくTwitter(X)やFacebookといったSNSです。だからこそ、そういうものが変に操作されてほしくない。おそらく大高さんがやっているクラウドファンディング(モーションギャラリー)に参加している人たちって、ジャーナリズム思考がかなり強い人だと思っていて。単純に映画が好きとか面白いという理由で共鳴しているだけじゃなく、ジャーナリズム的な視点で物事を捉え、こういうつくり手が世の中にいることを社会に伝えたい、という強い意志を持っている人たちなんじゃないかな……。
大高:確かにそうかもしれません。
茂田:ニッチな音楽が評価された時代って、個人ジャーナリズムの力がすごく影響していたりするんです。マニアックな雑誌や新しいメディアが生まれるときも同じです。個人の影響力の高まりが多様性を育むことにつながるとすれば、個人の理想を大いに語るメディアを立ち上げることにもそれなりに意味があるんだろうと思っています。
一方、みんなでつくるものってそうしたマニアック性が薄れるというか、結果的に誰ひとりのエゴも貫かれないという側面がありますよね。シネコンで上映される大資本の映画なんかがまさにそうなのかもしれない。そう考えると、ミニシアターで上映される映画って個人ジャーナリズムの精神が息づいた自費出版の印刷物に近い感じがするんです。
大高:自費出版って、いいですよね。宮﨑 駿も庵野秀明も、ある意味規模のでかい自費出版と言える。だから、みんながあれだけの熱量を携えて観に行くんでしょう。
茂田:だから、個人ジャーナリズムが何かの圧力で歪められるようなことはあってほしくないんです。豊かな文化土壌を形成するうえで、それがいちばんつまらないことだから。モーションギャラリーというクラウドファンディングには、そうした力に屈しないすごくフェアの世界があるんだろうと感じました。
——どういう作品に支持が集まるか、傾向があれば教えてください。
大高:やっぱりクリエイティブなプロジェクトですね。クリエイティブとは何かといえば、テンプレでやっていないものです。流行りの二番煎じには支持が集まりづらい。お金を出す人もそこはきちんと見ていて。ビジネス色の強い拡大再生産的なロジックが見えた瞬間にみんな冷めちゃう。それがクラウドファンディングのいいところであり面白さです。
先行割引を謳ったクラウドファンディングが増えているという話がありますが、安売りしないとお金が集まらないという発想はクラウドファンディングの本筋としては大きな間違いで、本来は逆です。確固としたビジョンやパーパスがないから価格弾力性を大きくしてお金を集めようとするのであって、僕から言わせれば多少高くても、「みんなが欲しいという未来を一緒につくりましょう。だからぜひ応援・参加してください」というのがクラウドファンディングの本来の姿なんです。そういうところに価値を見出せるクラウドファンディングが増えてほしいと思っています。

自分の考えを相対化し、考え方を捉えなおす機会にもなるのが文化表現の役割(大高)
大高:異なる価値観に触れることは、民主的な社会を形成していくうえでひじょうに重要なことだと思うんです。「自分は絶対に正しい」だけだと、最後はカルト的になってしまう。異なる考えに触れ、そこから学びを得ることで、よりよい発想を導き出してくれる——映画やアートはそういう機会を与えてくれるメディアだと思っています。自分の考えを相対化し、考え方を捉えなおす機会にもなるのが文化表現の役割です。そうして芽生えたひとつひとつの個性が社会の多様性につながっていくんです。
人は誰しも社会的にマイノリティな感情や体験をどこかに持っていて、それが自分だけだと思うと生きづらいですよね。でも、同じ思いを持つ人がどこかにいるとわかれば、死を思い止まらせることだってできる。映画のような文化表現は、そうした他者の存在を知る手がかりになることもできます。そういう意味で、映画は多様性を担保する仕組みと言い換えることもできるでしょう。経済一辺倒で、経済的に勝ったら最高、負けたやつは使えない、みたいな悪しき弱肉強食社会になると、もう多様性もへったくれもありません。そういう尺度とは違うもうひとつの軸として、文化が社会に強く存在していくことはとても重要でしょう。
茂田:映画や音楽をつくるとか絵を描く行為って、面と向かって言えないことをかたちにすることなんじゃないかと思ってるんです。もともと日本人はそういうことが苦手で、むしろ面と向かって発言しないことを美徳としてきた。だからこそ逆に、表現を通して何かを言葉にしたり、感情をぶつけることが向いているんじゃないかな。発言したいけれどインフラが整っていないからと不満を口にするぐらいだったら、その前にモーションギャラリーのような仕組みを活用してやりたいことをどんどん実現していってほしいし、そういう人が増えたら嬉しいですね。
クリエイティブという行為が仰々しいことではなく、もっと民主化・大衆化していってほしいんです。何も変わらない休みの日を過ごすくらいなら映画を観る、そういう習慣が根づいたら、きっと少数派の意見がなかったことにされない成熟した社会になるんじゃないかな。このメディアは、そういう仕組みをつくらない社会への不満を述べるのではなく、仕組みがないのはつくろうとしない熱量不足でもあるということを指摘し、奮起するきっかけになればと思っています。目指すのは、理想や思いをインタラクティブに交換できる社会。大高さんの取り組みはそれに向けた一歩だと感じているので多くの人に知ってもらいたいんです。
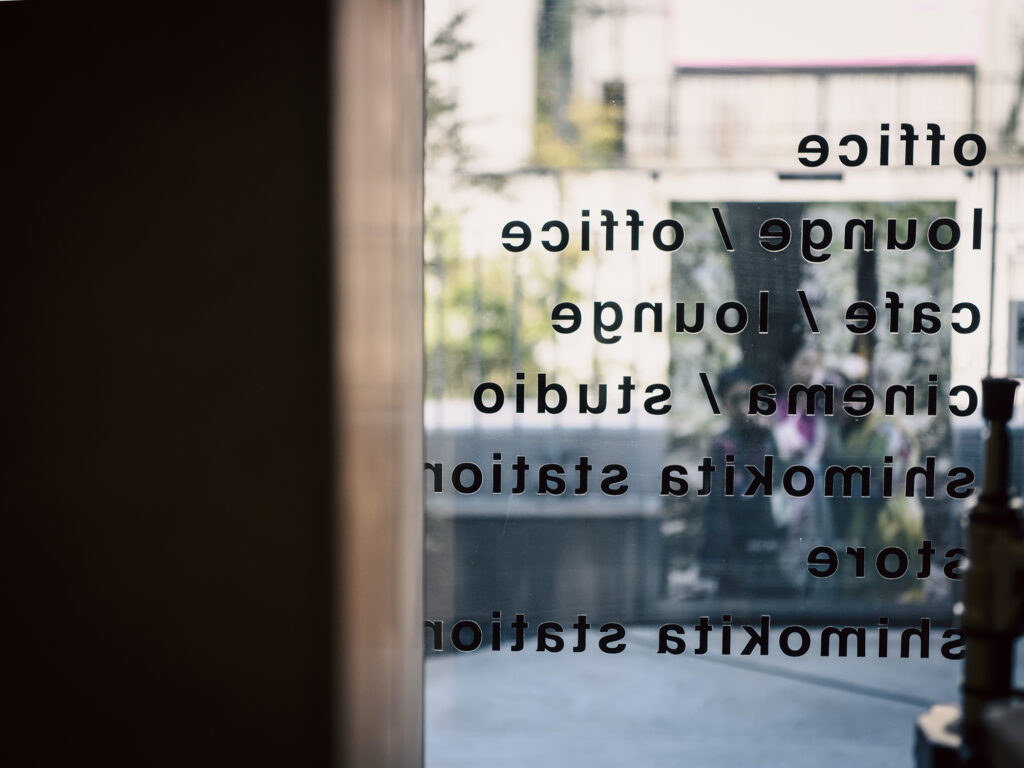
大高:メディアの立ち上げ以外に、今後やりたいと思っていることってありますか?
茂田:これからの世の中って、お金はないけど時間はあり余ってます、という状況がますます加速していくと思うんです。テクノロジーが進化し、人手をそんなにかけなくても社会が回っていくから。そのとき人に問われるのは、豊かな時間の使う方でしょう。
僕の生業は美容関係なんだけど、この仕事の本質を語るうえでひじょうに重要なのが「死生観」です。幸せに生きて幸せに死ぬっていったいどういうことなのか? そのことを改めて問う必要があると感じてます。時間はないけれどお金はある、という時代は不老不死に関心が向かったけれど、もうそういう状況じゃない。時間をどう使うと幸せに生きたと思えるか、そういった方向に関心や注がれるエネルギーはシフトしていくんでしょう。
僕は美容には3つの軸があると考えていて、ひとつは体の外側からアプローチする化粧品のような美容、もうひとつが体の内側から整える食のような美容、そして最後に精神がつくる美容です。化粧品をつくりながら食のイベントを行い、今回メディアを立ち上げたのもこうした考えに基づいていて、最終的には精神的に豊かに暮らすということがどういうことかをいろんな人に伝えたいんです。さまざまな人の思考に日々触れながら、自分のなかで小さなムーブメントを起こし続けていければマンネリ化することなく、多様で豊かな人生が送れるはずです。そういうメッセージをライフワークとして発信し続けたいんです。大高さんの展望も聞かせてもらえますか?
大高:考えていることはいろいろありますが、まずは来年K2の会員制度をスタートし、新しいミニシアター像を描いていくことです。今自分が考えているものが成立すればミニシアターの運営の新しいモデルになり得るし、後に続く人が出てくるかもしれない。若年層の映画人口が増えてより豊かになっていくかもしれない。そんなビジネス的発明ができたらいいですね。
茂田:僕は曽祖父が興した会社で仕事をしているんですが、じいさんや親父から帝王学や経営学みたいなものを教わったためしがないんです。だから、会社経営やリーダーとしての立ち居振る舞いについてはすべて独学なんです。ただ最近になって、ふたりの生き様から実はいろいろと教えてもらっていたと感じるようになった。家族で外食をするときは必ずふたりの贔屓の店に行くんですが、どの店も「初めまして」という応対じゃなく、「どうもこんにちは」という感じで迎え入れられたんです。通い詰めることで特別扱いされたいという意識はゼロではなかったと思うけど、それ以上にふたりには、好きな店が潰れちゃ困るという思いが大きかったんだろうと。贔屓の店に通うことが理想の社会を創造することだということをふたりはその生き様を通して示してくれてたんじゃないかと思うんです。
大高:なるほど、そうかもしれないですね。
茂田:ミニシアターがどうしたら存続していけるかを考えたとき、例えば投げ銭のような仕組みも有効じゃないかって思うんです。世の中には映画館がなくなったら困る人もいれば、そうじゃない人もいる。なのに料金は一律ですよね。大高さんが運営している映画館だったら、大高さんの志に対して値段を付けたい人もいるでしょう。なかには規定の倍の料金を払っても惜しくないと考える人もいるかもしれない。飲食店なんかでも、店で過ごした時間や雰囲気の満足度に対して、実際に食べた料理の金額は3,000円だけれど今日は楽しかったから1万円でいいよ、といったやりとりが客と店の間で自然に交わせたら楽しいんじゃないかな。
大高:そう思います。
茂田:自分の大事なものを贔屓にする。そういう自己決定も「社会彫刻」という考えに通じた行為であるという認識が定着していくといいなと思いました。

Profile
-
大高健志(おおたか・たけし)
早稲田大学政治経済学部卒業後、2007年外資系コンサルティングファーム入社。戦略コンサルタントとして、事業戦略立案・新規事業立ち上げ等のプロジェクトに従事。その後、東京藝術大学大学院に進学。制作に携わる中で、 クリエイティブと資金とのより良い関係性の構築の必要性を感じ、11年にクラウドファンディングプラットフォーム〈MOTION GALLERY〉設立。以降、70億円を超えるファンディングをサポート。2015年度グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト100」受賞 。22年、下北沢駅南西口直結のミニシアター、シモキタ-エキマエ-シネマ〈K2〉を開館。
同時にさまざまな領域でプレイヤーとしても活動。現代アート:2020年開催「さいたま国際芸術祭2020」キュレーター就任。映画:プロデューサー 『あの日々の話』(第31回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門選出)/『踊ってミタ』/『僕の好きな女の子』/『鈴木さん』(第33回東京国際映画祭「TOKYOプレミア2020」部門選出) 製作協力 『スパイの妻』(第77回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞受賞)/『蒲田前奏曲』/『脳天パラダイス』
-
茂田正和
音楽業界での技術職を経て、2001年より化粧品開発者の道へ。
04年より曽祖父が創業したメッキ加工メーカー日東電化工業ヘル スケア事業として多数の化粧品ブランドを手がける。17年、 スキンケアライフスタイルブランド「OSAJI」 を創立しブランドディレクターに就任。 21年にOSAJIの新店舗としてホームフレグランス調香専門店 「kako-家香-」(東京・蔵前)、22年にはOSAJI、 kako、レストラン「enso」による複合ショップ(鎌倉・ 小町通り)をプロデュース。23年は、 日東電化工業の技術を活かした器ブランド「HEGE」を仕掛ける。著書に、『食べる美容』( 主婦と生活社)、『42歳になったらやめる美容、はじめる美容』 (宝島社)がある。
Information
MOTION GALLERY
https://motion-gallery.net/
日本におけるクラウドファンディング・プラットフォームの先駆けとして 2011 年にスタートした、社会に新しい価値と多様性をもたらす創造的なプロジェクトを中心に構築されているクリエイティブ・コミュニティ。
社会彫刻家基金
https://socialsculptor.tokyo/
ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」の概念を現在の状況下で再解釈しながら実践するべく、アートを触媒に社会に変化を創り出すアーティストを支援する基金。
シモキタ-エキマエ-シネマ K2
https://k2-cinema.com/
「街の入口に、街の文化の共有地」をテーマに、東京・下北沢の線路跡地に2022年にオープンした駅直結のミニシアター。地元商店街の人々が出演する、本編上映前に流れるマナー動画にも注目。2024年1月より会員制度を開始予定。
-
写真:小松原英介
-
文:上條昌宏
NEWS LETTER
理想論 最新記事の
更新情報をお届けします
ご登録はこちら
ご登録はこちら
メールアドレス
ご登録ありがとうございます。
ご登録確認メールをお送りいたします。


